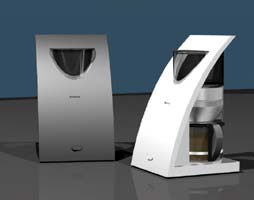デザイン依頼のコツ デザインを依頼する前に

「自社の技術や加工法、素材やノウハウを活かしたオリジナル製品をつくりたい!」
「自社製品をつくりたいけれどデザインや設計はできないし…販売も自社では難しい。」
「こんなアイデアがあるけれど…実現化するにはどうすれば?」
「商品化したい けれど、なるべく小ロットで開発したい」
「いままでのデザインイメージから抜け出せない!」
「製品リニューアルでデザインでの差別化をしたい」
さまざまな理由から 商品開発をすすめようとかんがえられます。
では、
どのように商品開発をすすめていけばよいのか?
はじめてデザイン事務所といっしょに仕事をしたい場合に、どのようなポイントを重視して決定すればよいのか
どのように指示をして、発注から商品化まで進めていけばいいのか
初めて依頼する場合、ノウハウがなく、よくわからないというのが実情です。
はじめて商品開発を依頼する
商品開発をしよう!ときまったら
まず何をすべきか
デザイン事務所などの選び方
できあがるまでのプロセスとポイント
基本的なポイントをきちんと押さえれば、
アウトソーシング先としてデザイン事務所をうまく活用することができます。
ぜひ、デザイン事務所を活用して新製品開発をすすめたいと考えている皆様に
役立てていただきたいと思っています。
次回は、はじめて商品開発をしようと決まったら まずすること をご紹介します。
「つくりたいモノの目的を明確にする」
製品開発をしよう!新しい製品企画をすすめよう!と考えているということは
新しいアイデアや改良したい製品、きっかけがあるはずです。
それぞれの企業にさまざまな背景と事情があると思います。
やろう!ときまったら、
次にさまざまな角度から検討をはじめましょう。
でも、待ってください。
「どこの会社に発注すれば良いのだろう?」
「いくらぐらい費用がかかるのだろう?」
「予算はどのくらい捻出できるだろうか?」
「費用がかかりそうなのですこしでもやすくしたい」
といったことを検討するのではありません。
では
まず何をするべきか
「企画・コンセプト」を練りましょう。
商品開発は「企画・コンセプト」と「計画」が肝心です。
はじめに、終わりがみえるといわれるぐらい、ここが肝心です。
なにをしたいのかを みつめなおす
新製品開発をしたい、改良をしたい などには きっかけがあったと思います。
そのきっかけからもう一度「企画・コンセプト」をみなおしてください。
何も立派な企画書を書くのではありません。
開発をすすめるうちに、さまざまな問題や追加要素がでてくると、
最初の目的が揺らいでしまう会社がすくなくありません。
・この商品は、何を社会に訴えるものだったのか
・他と何を差別化したかったのか
この2点だけでもはっきりとさせることが今後の商品開発をスムーズに進める上で重要となります。
そして、これを「記録」として残しておきましょう。
企画書のようにまとめるのが難しければ、
どんな人にどんなふうにつかってほしいのか。を思い浮かべましょう。
つまりターゲットユーザーです。
使う人は男性?女性?
使う人の年齢は?
どのような商品が好きな人でしょうか?
室内で使うものであれば、どんな部屋にある商品か?
そして、
似た商品がありますか?
こんな雰囲気にしたいという商品はどれでしょうか?
少なくてもこういう点を出来るだけ客観的に整理してはっきりしていれば、
商品としても魅力が何なのか、
どこが差別化されるのかがはっきりしてきます。
発注する側の企画・コンセプトがゆらいでしまっては、
どんな優秀なデザイナーでも的確に提案することは難しくなります。
途中で目的がかわってしまっては、
せっかく費用を投じて依頼しても、最大の効果を得られることはできません。
これら情報をデザイナーと共有して、
はじめて「デザイン」にとりかかれるのです
企業の得意分野が活かされているか
企画の「目的」がはっきりしたら、
次は、得意分野や専門技術が活かされているか?を検証してみます。
それぞれの企業には得意分野や専門技術があります。
個人でも同様です。
それらを活かすことのできる商品開発であれば、
より成功に導くことができます。
長い間にわたって鍛えぬき、蓄積してきた技術や知識を活かす商品であれば、
より差別化された商品となります。
とりわけ、新しい事業分野へと進出していった場合、
かならずといっていいほどその分野にすでに進出している商品が存在しています。
たちまち、その商品との競争にさらされてしまいます。
そこで活かされるのが、
独自の技術や知的財産(知恵、知識など)です。
プラスアルファーの一味違う「何か」を持っていることで、
新規事業の可能性が見い出せます。
どこに発注する?
商品開発の目的がかたまってきたころには、
内容をどうしようかという事とともに、どこに発注すればよいかが問題になってきます。
色々情報を集めてみると費用も心配だし、
社内や知り合いにちょっとお願いしてすすめられないだろうかという話もでてくるかもしれません。
絵がうまいやつに頼もう
趣味でCGをしてる若い者にまかせられないか? という話もでてくるかもしれません。
CGやCADを使えば、簡単に立体物のイメージができます。
ただ、それでは、絵ができただけであったり、なんとなくかたちになった感じがぬぐえないでしょう。
絵やかたちをつくるためならCGやCADを使えばだれにでも手軽にできるようになってきました。
ただ、かたちを「整理する」「質をたかめる」ことは、デザイナーでなければできないことかもしれません。
予算がないから社内ですすめた。
でもなんとなく商品ができただけで、お客様の反応はよくない。…では
せっかくの新商品がなきます。
多くの費用を投じてすすめた開発が無駄になります。
これだけは避けたいものです。
ここまでで、依頼するのに必要な「企画・コンセプト」の準備が整いました。
どのデザイン事務所と仕事をする?
大企業であれば、多くの開発事例があり、経験もノウハウも蓄積されています。
ところが中小企業で、頻繁に商品開発を依頼することはありません。
そのため、
いざ依頼しようにも、どのようにデザイン事務所を選べばいいのか、
どんな風に依頼すればよいのか、に困る。とのご意見をよく伺います
特に、はじめてだと、不安も大きいです。
そこで、選ぶポイントとして
デザイン能力と専門性、得意分野をみきわめてください。
デザイン事務所を選ぶポイント
デザインを依頼するときに
「知恵」「知識」と「技術」を備えていることが基本です。
「知恵」とは、先見性や企画構築能力、
「知識」は、製造や加工の知識、素材、構造など、
「技術」とは、造形能力、設計能力などです。
はじめて商品開発をする場合には、
商品開発をすべてコーディネイトしてくれる、
特に、「設計対応能力」、
製造や加工の知識に基づく『製品設計』が きちんとできるかどうかが重要です。
デザインのみを依頼し、設計を自社で行う場合でも、
「設計」「製造」を知らずに「デザイン」されたものは、
製造するにはコストがかかりすぎたりすることがあります。
「商品」になることを前提にデザインされていることが大切だからです。
「デザイナーに頼んでみたがどうやっても製品化することができなかった」
というような話があるのは、
この「製品設計」能力が十分でないデザイナーに依頼してしまった結果です。
商品開発は商品の「絵」が必要なのではなく、
商品化できること必要なのです。
製造や加工の知識がなく、
またそれを反映させる設計能力がなければ、「商品」にはなりません。
「スケッチ」や「CG画像」だけでは、「商品」になりません。
絵を渡されて、あとは製造の方にお願いすればいいですよ。といわれたとしても
実際に、設計をすすめようとすると、
設計者から 「この形状ではできない、製品化できない」と言われることにつながります。
これは、3次元CADデータであっても同じです。
金属を曲げて作るのか、樹脂を金型で成形するのかでは、設計要件が大きく違います。
この設計要件を満たしていないCADデータは、
製品化するために再設計をしなければならず、
逆にコストがかかる結果になります。
コミュニケーション力・コーディネイト力を確かめる。
デザイン能力と専門性、得意分野を見極め、
次に、中小企業との商品開発を多く手がけているデザイン事務所を探すべきでしょう。
いうまでもなく、
大企業と中小企業では、組織、強み、経営はまったくちがうところばかりです。
中小企業の持つ企業資源を最大限に活用する方法を理解し、
さまざまな経験をつんでいることが重要です。
問い合わせる中で、見極めるべきポイントの1つです。
また、
自社のみで開発することが難しい商品の場合、
デザイナーの持つネットワークを活用してさまざまな企業とのマッチングも可能となります。
アイ・シー・アイデザイン研究所では…
デザイン・設計など商品開発に必要な項目に対するヒアリングを行います。
企画・コンセプトが、はっきりとかたまっていない段階や
はじめて商品開発をしたいので、どうすすめてよいのかわからない。
そのような場合のご相談にも対応しております。